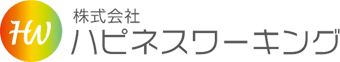研修を実施したけれど、みんなすぐに内容を忘れてしまう。
研修の満足度が低かった。
研修をしても何も変わらない。
そんなお悩みをお持ちではないですか?
研修は、社員の行動変容やチーム力強化、職場改善など
何かしらの「変化」を起こすために行うものです。
忙しい社員を集めて、費用をかけて行うわけですから
「結果」を出したいですよね。
でも、結果が出ない場合が多いのが現状ではないでしょうか。
それはなぜか?
答えは、設計が間違っているからです。
私自身、年間150本の研修の依頼を受けます。
しかしその多くが
「毎年やっている研修なのでお願いします」
「社内のコミュニケーションをよくしたいので、傾聴の研修をお願いします」
「内容はお任せしますので、新しいトピックでお願いします」
といったご依頼です。
とても表面的なご依頼です。
もっと言えば、研修を甘く見過ぎています。
その依頼自体が、失敗の要因です。
現在の問題は何か。
会社の目標に対して、社員にどんな力をつけてもらいたいのか。
研修でどう変わったもらえたらいいのか。
・・・そういったことを分析し、
何のために研修を行うのかを考えてテーマを選び、
どのような内容にするのか、行動変容が定着するために何を行うのか。
これらを練り上げることが、研修設計です。
例えば、ハラスメント防止研修。
多くの企業は、
ハラスメントの定義や、何をしてはいけないのかを教える研修を行っています。
プラスアルファで、アンガーマネジメントを教えたりします。
でも、それでハラスメントはなくなりますか?
残念ながら、何も変わらないでしょう。
下手をすると、もっとギスギスし、メンタルヘルス不調者が増えるかもしれません。
ハラスメントをしてはいけないことなんて、みんなわかっています。
でも、人間が集まるといじめは起きてしまいます。
そういう構造的なことを考えずに
ただただ知識を教えてもうまくいきません。
ハラスメントは組織の構造上の問題ですから、
経営者含め全員が参加して行うべきです。
しかしほとんどの企業で、
ハラスメントの研修に経営者が参加することはありません。
・・・少し話が逸れましたが、
何のために、どうなりたいのかを考えて
じっくり研修の設計をすること。
これが成功の土台であるということです。
満足度が高いのがいい研修ではありません。
行動が変わるのが、研修のゴールです。