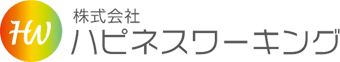「制度はあるのに、なぜかみんな休まない。」
「“無理しないで”とは言っているけど、実際には休む人が少ない。」
そんな悩みを抱える企業やリーダーは少なくありません。
“休む文化”を職場に根づかせるには、ルールや制度だけでは不十分です。
必要なのは、日々の言葉・声かけ・態度の積み重ね。つまり、コミュニケーションそのものです。
今回は、リーダーや人事が使える、“休んでいい”を当たり前にするための具体的な言葉の選び方と会話例をご紹介します。
1.まずは「休むことは悪いことではない」というメッセージを届ける
社員が最も恐れるのは、「休んだら評価が下がるのでは」という不安です。
その不安を和らげるためには、明確に「休んでいい」と言葉で伝える必要があります。
✔ メッセージ例
「忙しい時こそ、しっかり休むことが大事です」
「パフォーマンスを保つために、意識して休みを取ってください」
「〇〇さんがしっかり休めるように、チームでフォローする体制を整えましょう」
“休むと迷惑をかける”という思い込みを、「休むのは戦略」と言い換えることがポイントです。
2.相談しやすい雰囲気をつくる声かけ
「体調が悪い」「家庭の事情がある」といったことを、上司に打ち明けにくいと感じる社員は多いもの。
相談を引き出すには、上司から“聴く姿勢”を示すことが必要です。
✔ 会話例
「最近、ちょっと顔色が疲れてるように見えるけど、無理してない?」
「もし何かあれば、いつでも話聞くからね。遠慮しなくていいよ」
「今の業務量、ちょっと多すぎるかもね。一度、整理してみようか」
“相談してもいいんだよ”というメッセージを、雑談の延長でさりげなく表現するのがコツです。
3.休む社員へのポジティブなリアクション
「明日、休ませていただきたいです」と言ったとき、上司や同僚がどう返すかで、職場の空気は大きく変わります。
✔ 応答例
「ゆっくり休んでね。何かあればこちらで対応するから」
「ナイス休暇!いい時間にしてきて」
「リフレッシュして、また元気な顔を見せてね」
NGなのは、
「この忙しい時にか…」
「その分、こっちは大変になるなあ」
といった「冗談めかした嫌味」。
本人の心にダメージを残してしまいます。
4.有給休暇の取得を促すときの言い方
「休んでいいよ」と言われても、休みにくいのが日本の職場文化です。
そこで有効なのが、休むことを“個人任せにしない”声かけです。
✔ 会話例
「有給の取得状況を確認したら、〇〇さんまだあまり取れていなかったので、調整しませんか?」
「今年の残りの有給、計画的に使っていきましょう」
「仕事の状況を見て、〇日あたり休めそうですね。一緒に調整しましょうか」
このように、“組織の側から働きかける姿勢”があると、休みやすさが格段に上がります。
5.ミーティングで使えるメッセージ
定例ミーティングや朝礼は、職場の空気をつくるチャンスです。
短い一言で、「この職場では休んでもいい」という共通認識を育てましょう。
✔ 使えるフレーズ
「体調がすぐれないときは、無理せず休んでくださいね」
「忙しい時期ですが、適度に休みながら進めていきましょう」
「最近休めていない人は、ぜひ調整してリフレッシュしてください」
月初や繁忙期前など、タイミングを見て“先に言っておく”ことで、心理的ハードルを下げられます。
6.休暇復帰後のフォローコミュニケーション
休んだ後に職場復帰する際、「なんとなく気まずい」「申し訳ない気持ちになる」人もいます。
復帰直後の一言で、その不安を和らげましょう。
✔ フォロー例
「おかえりなさい!ちゃんと休めましたか?」
「リフレッシュできたようで良かった。戻ってきてくれて嬉しいです」
「お休み中の分はフォロー済みだから、無理せずペース戻してくださいね」
“復帰を歓迎する文化”を言葉で示すことが、次の休暇申請にもつながります。
7.「いいかげん=良い加減」な働き方を言語化する
最後に、働き方そのものについて、「いいかげん(良い加減)な働き方を認める言葉」が大切です。
✔ 言い回し例
「完璧じゃなくてもOK。まずは動いてみよう」
「60点の時点で共有して、チームで仕上げよう」
「疲れてる時は、ちゃんと休むのも生産性のうちだよ」
このような言葉が繰り返されることで、真面目さ一辺倒ではない柔軟な職場文化が育ちます。
おわりに
休む制度があっても、実際に人を動かすのは、日々の言葉と態度=空気です。
「こんなこと言っても大丈夫なんだ」
「この職場は、ちゃんと休めるんだ」
そう思える瞬間を、リーダーや人事のコミュニケーションで少しずつ増やしていくことが、真の“休む文化”をつくる第一歩です。