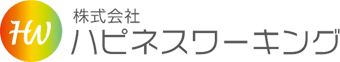メンタルヘルス対策の捉え方が、
従来の「病気になった人への対応」から「すべての従業員の心の健康づくり」へと、大きく変化しています。
これまで多くの企業では、メンタルヘルス対策というと「うつ病などの精神疾患を予防する」「休職者への対応」といった疾病対策に重点が置かれてきました。
もちろん、これらの対策は非常に重要です。しかし、それだけでは不十分なのです。
メンタルヘルス対策の本質は、従業員一人ひとりが心身ともに健康で、いきいきと働ける職場環境をつくること。
これは単に「病気でない状態」を目指すのではなく、「ポジティブな心の健康」を育むことを意味します。
従業員が自分の能力を十分に発揮でき、仕事にやりがいを感じられる状態こそが、本当の意味での心の健康です。
健康経営指標の変更は何を意味している?
この視点転換を象徴するのが、健康経営優良法人2026年度の変更点です。
これまで「メンタルヘルス対策」という項目名だったものが、「心の健康保持・増進に関する取り組み」へと変更されました。
この名称変更には重要な意味が込められています。
それは、メンタルヘルスの取り組みが従業員自身の能力発揮につながることを明確に認識し、
より積極的な健康づくりの視点を取り入れるということです。
つまり、問題が起きてから対処するのではなく、日常的に心の健康を育み、
従業員一人ひとりが自分の持てる力を最大限に発揮できる環境づくりを目指すという姿勢の転換です。
メンタルヘルスは、マイナスをゼロにするだけでなく、プラスをさらに上に引き上げることでもあり、
私たち専門家は「ポジティブメンタルヘルス」の普及に努めてきましたから、
メンタルヘルス=疾病対策と片付けられてしまっているように感じ、
少々残念さは感じているのですが…。
……気を取り直して。
また、健康経営優良法人2026年度の認定基準では、
PHR(Personal Health Record)の活用促進や、
性差・年代を踏まえた職場づくり、
育児・介護と仕事の両立支援なども新たに評価項目に加わりました。
これらは、多様な背景を持つ従業員一人ひとりが、それぞれの状況に応じて健康に働ける環境を整えることの重要性を示しています。
4つのケアの統合的アプローチ
職場のメンタルヘルス対策では、
従来から「4つのケア」という考え方が提唱されています。
セルフケア、ラインケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケアです。
しかし、これらを効果的に機能させるには、疾病対策だけでなく、心の健康づくりの視点を統合する必要があります。
セルフケアでは、ストレスへの対処法だけでなく、
自己理解を深め、自分の強みを活かす方法や、
仕事の意義を見出すプロセスをサポートすることが重要です。
従業員が自分の心の状態に気づき、前向きに維持・向上させる力を育てることが、長期的な心の健康につながります。
ラインケアでは、管理職が部下の不調のサインに気づくことも大切ですが、
それ以上に、日頃から部下一人ひとりの強みを理解し、成長を支援する関わりが重要です。
心理的安全性の高い職場環境をつくり、メンバーが安心して意見を言えたり、
互いに協力し合える雰囲気を醸成することが、チーム全体の心の健康を高めます。
予防から促進へのパラダイムシフト
私が20年間の現場経験で確信を持って言えることは、
メンタルヘルス対策を「病気の予防」だけで捉えていた企業よりも、
「心の健康づくり」として捉えている企業の方が、結果として離職率も低く、従業員満足度も高いということです。
心の健康づくりには、ワーク・エンゲージメント(仕事への熱意や没頭、活力)を高める取り組みも含まれます。
従業員が仕事に意味を見出し、自分の成長を実感できる環境があれば、
多少のストレスがあっても、それを乗り越える力が育ちます。
これは単なるストレス耐性とは異なり、より積極的で持続可能な心の健康状態です。
また、組織風土そのものを見直すことも重要です。
長時間労働が常態化していたり、失敗を許さない雰囲気があったり、コミュニケーションが不足している職場では、
どんなに個別のケアを充実させても限界があります。
働き方改革や、心理的安全性の確保、多様性の尊重といった組織レベルでの取り組みが、心の健康づくりには不可欠です。
これからの実践に向けて
これからメンタルヘルス対策に取り組む、
あるいは既存の取り組みを見直す際には、
次の点を意識していただきたいと思います。
まず、メンタルヘルス対策を「コスト」ではなく「投資」として捉えることです。
従業員の心の健康は、生産性向上、創造性の発揮、離職率の低下など、様々な形で組織に還元されます。
特に2026年度からの健康経営の考え方では、こうした効果検証や経営レベルでの関与も重視されるようになっています。
次に、経営トップから現場まで、全員がメンタルヘルスを「自分ごと」として捉えることです。
人事部門や産業保健スタッフだけの問題ではなく、経営戦略の一環として、
また日々のマネジメントの重要な要素として位置づけることが大切です。
そして、多様性への配慮です。
2026年度の健康経営指標でも、性差や年代を踏まえた職場づくりが評価項目に加わりました。
女性の健康課題、高齢従業員への対応、育児や介護との両立など、一人ひとりの置かれた状況は異なります。
画一的な対策ではなく、多様なニーズに応える柔軟な取り組みが求められています。
職場のメンタルヘルス対策は、疾病対策という狭い枠組みを超え、
すべての従業員がいきいきと働き、自分の能力を最大限に発揮できる環境づくりへと進化しています。
これは単なる理想論ではなく、健康経営指標の変更にも示されているように、
企業経営の重要な戦略として認識されつつあります。
20年間、様々な職場と従業員を見てきた私の経験から言えることは、
心の健康づくりに真剣に取り組む組織ほど、従業員も組織も共に成長し、
持続可能な発展を遂げているということです。
これからの時代、職場のメンタルヘルス対策は、
問題解決型から価値創造型へとシフトしていくでしょう。
疾病対策の重要性を認識しつつも、それを土台として、すべての従業員の心の健康を育み、
一人ひとりが輝ける職場づくりを目指していただきたいと思います。