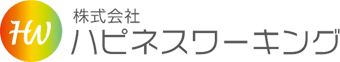カウンセラーとして20年間、多くの働く人々の心の声に耳を傾けてきました。
その中で強く実感するのは、ワーク・エンゲイジメントと働きがいが、これからの職場に不可欠な要素だということです。
人生の大部分を占める仕事
私たちは人生の約3分の1を仕事に費やしています。
週5日、1日8時間以上を職場で過ごす現実を考えると、その時間が充実しているかどうかは、人生の質そのものを左右します。
ワーク・エンゲイジメントが高い状態とは、仕事に対して活力、熱意、没頭を感じている状態のことです。
仕事に対して前向きで充実した心理状態にあることを指します。
相談室で多くの方とお話ししていると、「仕事がつまらない」「やりがいを感じられない」という声をよく耳にします。
そうした方々の表情は暗く、肩も重そうに下がっています。
反対に、仕事に情熱を持って取り組んでいる方は、疲れていても目に輝きがあり、話し方にも活力があります。
ワーク・エンゲイジメントの高低が、その人の人生満足度にも直結しているのです。
個人のウェルビーイングへの影響
ワーク・エンゲイジメントが高い人は、仕事から得られる達成感や成長実感によって、自己肯定感・自己効力感がさらに向上します。
自分の能力を発揮し、組織に貢献できている実感は、人間の基本的な欲求である「有用感」を満たします。
これは、マズローの欲求階層説でいうところの承認欲求や自己実現欲求の充足につながります。
私がカウンセリングで出会った多くのケースでは、仕事での充実感が家庭生活にも良い影響を与えています。
仕事で活力を得ている人は、家族との時間も大切にし、趣味や自己啓発にも積極的です。
これは「スピルオーバー効果」と呼ばれる現象で、仕事での前向きな感情が私生活にも波及するのです。
逆に、ワーク・エンゲイジメントが低い状態が続くと、抑うつ症状や不安症状、さらには燃え尽き症候群のリスクが高まります。「月曜日が来るのが憂鬱」「朝起きるのがつらい」といった訴えは、危険信号です。
長期間このような状態が続くと、身体的な症状として頭痛や睡眠障害、胃腸の不調なども現れてきます。
組織にとってのメリット
組織の立場から見ても、従業員のワーク・エンゲイジメントを高めることは極めて重要です。
エンゲイジメントの高い従業員は、自発的に行動し、創造性を発揮し、困難な状況でも粘り強く取り組みます。
これは、変化の激しい現代のビジネス環境において、組織の競争力を大きく左右する要因です。
研究データによると、エンゲイジメントの高い職場では、離職率が低く、生産性が高く、顧客満足度も向上する傾向があります。従業員が仕事に情熱を持って取り組むとき、その熱意は顧客にも伝わり、より良いサービスや製品の提供につながります。
また、チームワークも向上し、職場の雰囲気が明るくなることで、新たなアイデアが生まれやすい環境が形成されます。
人材の定着という観点でも、働きがいのある職場は強力な魅力となります。
優秀な人材を採用し、長期間活躍してもらうためには、単に給与や福利厚生を充実させるだけでは不十分です。
その人が持つ能力や価値観に合った仕事を提供し、成長の機会を与え、貢献を正当に評価する環境を整えることが必要です。
社会全体への波及効果
ワーク・エンゲイジメントの向上は、社会全体にも大きな恩恵をもたらします。
働く人々が充実感を持って仕事に取り組める社会は、イノベーションが生まれやすく、経済活動も活発になります。
また、メンタルヘルス不調による医療費や社会保障費の抑制にもつながります。
現在、日本では少子高齢化による労働力不足が深刻な課題となっています。
この状況下で、一人ひとりの生産性と創造性を最大限に引き出すことは、社会の持続可能性を支える重要な要素です。
ワーク・エンゲイジメントの高い職場は、多様な人材が活躍できる環境でもあり、女性や高齢者、外国人労働者など、様々な背景を持つ人々の能力を引き出すことができます。
これからの時代に向けて
AI技術の発達により、定型的な業務は自動化される一方で、人間にしかできない創造的な仕事や対人関係における仕事の価値が高まっています。
このような変化の中で、従業員一人ひとりが主体的に考え、行動し、学び続ける姿勢が求められます。
そのためには、仕事に対する内発的な動機、つまりワーク・エンゲイジメントが不可欠なのです。
カウンセラーとして、私は今後も職場のメンタルヘルス向上に貢献していきたいと考えています。
ワーク・エンゲイジメントと働きがいを高めることは、個人の幸福、組織の成功、そして社会の発展という三重の価値を生み出す取り組みです。
これからも、一人でも多くの人が充実した職業生活を送れるよう、支援を続けていきます。